※本記事は冬組第十二回公演『黄天ノ種火』のイベントストーリーのネタバレを含みます。ご了承のうえ閲覧ください。
Contents
Intro:キッカケは筆者と誉の「相容れなさ」!?
性格類型論の16タイプ理論において私と誉は同じ性格タイプです。
しかし、私は根本的に有栖川誉という人物の行動原理についてほとんど共感できません。
いわば「分かりあえないことをわかりあった」状態。根本的に、水と油なのです!
そもそも16タイプ理論は、人がどう情報を感受し、どう判断するかのパターンを分類したものなので、そのパターンが何のために使われているか?ということまではわかりませんから、こういった差異が生まれるのも当然ではあります。
でも、この差異を説明できるのは、一体何なのか!?
そこで私が着目したのは、準主演の雪白東との対比でした。
仮説:動機を司る2つの方向性
東との対比から見えてきたのは、誉と東とでは行動の動機、つまりは16タイプ理論が示す心理機能が何のために使われているか?の方向性がまるで違うということでした。
この動機を説明するために参考になるのが、心理学者デイヴィッド・バカンが1966年に提唱した「人間の二重性概念」です。
|
|
この概念は、単に人間を二つのタイプに厳密に分けることではなく、互いの要素がバランスを取ることで人は健全に生きられるとされています。
抽象的な話が続いてもよくわからないと思いますので、早速この二重性概念を応用してストーリーを考察してみたいと思います!
比較検証!冬組第十二回公演『黄天ノ種火』イベントストーリー
まずは、彼らが本当にエージェンシー/コミュニオン的な動機を持っていると言えるのか?を考察していきましょう。
エージェンシー:雪白東
今回の公演で綴が用意した脚本では、主演の兄である子土という役が物語の結末で死を迎える設定となっていました。
東はその脚本を読んで、「この役を演じたい」と自ら立候補。
過去に家族を失い、兄への特別な想いを抱える東ですが、そんな経験をした自分だからこそ、この役を演じることで役者としても人間としても成長したい…という野心を顕にしています。
 (冬組第十二回公演『黄天ノ種火』より)
(冬組第十二回公演『黄天ノ種火』より)
おっとりしていて優雅な印象のある東ですが、そのイメージとは裏腹に、行動の背景を見てみると、実はとてつもないストイックさを持っています。
過去にも、自らが主演公演を務めた冬組第三回公演『真夜中の住人』では、孤独を受け入れる玲央という役を演じるために、孤独を身をもって経験する役作りをしました。
家族の事故があって、「一人で朝を迎えるのが苦手」と言っていた東ですが、それでもなお、敢えて孤独な環境に自分の身を置く…といった行動をしているんですよね。
どちらの役作りも、自分の人生の経験を受け入れ他の誰にも出せない個性を出そうとする傾向が際立っています。
「自分の力で生きる」ための繋がり
そもそも「誰かと深く繋がりたい」と劇団に入った東が、どうしてエージェンシーなの!?コミュニオンなんじゃないの?と思う方も多くいらっしゃるかと思います。
そもそもなぜ東は誰かと深く繋がることを求めていたのでしょうか?
これまでのストーリー内において一貫して「自分が寂しさを感じずに済む状況」を求めており、そのために誰かと深く繋がることによって心細さがなくなるだろうと話しているんですよね。 (メインストーリー第4幕『もう一度、ここから。』より)
(メインストーリー第4幕『もう一度、ここから。』より)
そう、東のセリフをきちんと読むと、別に一人でいることを否定してるわけではないことがわかるんです。
孤立、一人でいる状態そのものを嫌だと感じているわけではなく、その状態が引き起こす「寂しさ」の感情を克服したがっているんですよね。
冬組第七回公演『ホテルコンパス』においても、東が添い寝屋をしていた理由が語られていますが、誰かを元気づけるためという動機よりも先に「自身の孤独を救ってもらうため」であったと語っています。
つまり東が求めていたのは、他者そのものではなく、他者との関わりによって自分の孤独を乗り越え、自分一人でも立てるようになることだったのです。
このことからも、他者や集団との『結合』を目的としているわけではなく、あくまで個人の確立を目的としていることがわかります。
このように、東は役作りにおいても人生の選択においても、他者や社会との繋がりをゴールにしているわけではありません。
もちろん役作りを通して東が良い芝居をしたり、添い寝屋さんの仕事を通して結果的に顧客は喜びますが、それはあくまでも結果論。東自身の行動の動機はあくまでも『雪白東』という一個人を確立することにあります。
このことから、東は自己を確立し、境界線を明確にするエージェンシー的な傾向が強いと言えるでしょう。
エージェンシー/コミュニオンという二重性概念が説明しているのは、人間の根幹にある動機のこと。表層的な言葉で見えるものではないのです。
コミュニオン:有栖川誉
対する誉についてまず触れておきたいのは、彼の自己認識の根幹でもある過去の出来事。
元恋人に「壊れたサイボーグ」と評され、拒絶された経験です。
この経験は、誉の中で「自分は人の心がわからない欠陥品だ」という根深い自己評価を形成させてしまいました。

(冬組第十二回公演『黄天ノ種火』より)
ここで注目したいのは、そもそもなぜ誉がたった一人の恋人に言われた一言で自身のことを欠陥品と定めつけてしまったのか?という点です。
もちろんこれはガイの言っていたように、他のことが器用にできるから、たった一つの欠点が致命的に感じてしまったという理由もあるかもしれません。
しかし、ここまで致命的な欠陥と認識してしまった…ということは、それが誉の中で大きな問題を引き起こしていたということでもあります。
上記の引用でも「……誰かを慰めることなどできないということだろう。」と言っているとおり、誉はそもそも根本的に他者の役に立ちたいという動機が強く、それが達成できないことを大きな問題と認識してしまった、というのが道理でしょう。
誰かの悲しい姿をある意味で「見ていられない」ような感覚がありそうなのは、メインストーリー第4幕にて、険悪な冬組の様子を見て不和を解決しようとしたシーンからも見て取れます。
その鋭すぎる洞察力により仲間たちを傷つけることにもなってしまいましたが、そもそも誉の動機は後にも語っていたように軋轢をなくし問題を解決したかっただけなのです。
このように、誉の行動には、他者や集団の状況を敏感に察知し、その関係性を良好に保とうとする傾向が表れています。
「共同体」のための自己研鑽
あらゆる芸術に挑戦し、自分の可能性を拡張しようとする誉は、むしろエージェンシー的では!?と思う方も多いでしょう。
しかし、彼の挑戦の動機を振り返ると、むしろ逆であることがわかります。
まず、誉の原体験である絵本作家である父の個展にて、誉が何より関心を寄せたのは作品そのものではなく、それを見て満足する「鑑賞者」という他者の存在でした。
(冬組第十二回公演『黄天ノ種火』より)
誉の挑戦は、常に「誰か」を喜ばせたい、という願いから始まっているのです。
東の解説では「顧客の満足はあくまでも結果論である」と述べましたが、誉にとっては逆に顧客の満足こそが自分が目指すべきゴールだと幼いながらに認識していたということです。
また、何でもできて、何にでもなれる!と自認していながらも、芸術家以外を志さなかったところにも、あくまでも家族や共同体の価値観に結合し、その中で役割を果たそうとする傾向が伺えます。
誉ほど知的好奇心が旺盛で柔軟な発想を持っていれば、芸術という枠からはみ出して挑戦をすることも考えられますが、誉はあくまでも家族との関係性を保てる範疇での挑戦にとどめています。
そして、最終的には詩人という職業を選びましたが、その大きなキッカケは友人に勧められた詩作コンテストで大賞を取ったという、まさに「共同体」からの承認でした。
つまり、誉の挑戦とは、一貫して「共同体」に認められ、その中でより良く貢献するための挑戦であることがわかります。
これは、自己の内部基準で挑戦を続ける東とは、その動機が根本的に異なっています。
このように誉の行動は『他者との関係性』『共同体への貢献』を根本的な動機としていることがわかります。
誉も自己を拡張しようとする挑戦を行ってはいますが、それはあくまでも他者や共同体の関係性を前提としているのです。
「人の心がわからない」という深い悩みを抱えてしまっていたのも、まさに共同体の承認を根源的な動機として生きてきた証拠なのです。
過ぎたるは及ばざるが如し:二重性概念の「緩和」
こうして見てきたように、東は「個の確立」を、そして誉は「他者との結合」を、それぞれ追求してきたことがわかります。
しかし、今回のストーリーではお互いにもう一方の動機の作用により、公演を成功させていくことになります。
東の「境界線」をほんの少し溶かす丞
東は前述の通り、今回の子土役を自らの成長のための使命であるかのように受け止め、自ら役に立候補しました。
この東の自己成長をしようとする向上心や、役者としての高みを目指すストイックさはもちろん素晴らしいことですが、その素晴らしい克己心も「行き過ぎる」とかえって、弊害を生む結果となることも…。
東の場合は特に、通常は避けたくなるような深い精神的な苦痛を伴うわけですから、その重圧も大きなものでした。
そんな東を気にかけ、声をかけたのは丞です。
丞もまた、東のようにエージェンティックな自立心を持ちますが、だからこそ東のその姿勢に危なっかしさを感じたところもあるのでしょう。
東がしていることは、さながら命綱をつけずにロッククライミングをするかのような挑戦であり、下でハラハラしながら見ている丞の身になれば、まぁ納得でもあります(笑)
そして、丞の態度で特徴的なのは、「献身的であたたかな寄り添い」というものではなく、東の主体性を尊重した絶妙な距離感での支援です。
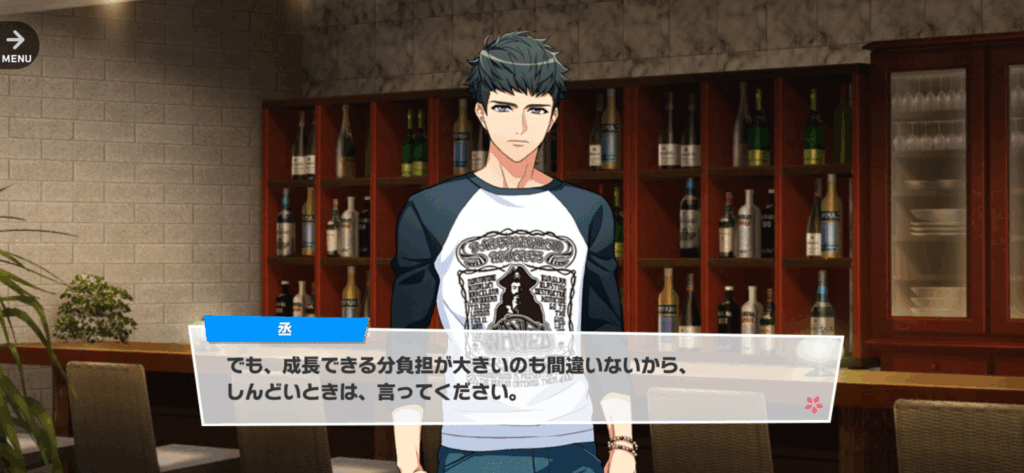
(冬組第十二回公演『黄天ノ種火』より)
丞は東と一緒に協働的になにかを成し遂げるわけではありません。
あくまでも「しんどいときは、言ってください。」なので、お互いの自律性は保たれている…。一人だけど孤独ではない、という絶妙さがあります。
東のような自立心が強いタイプの人は、過度に境界線を溶かされすぎてしまうと、自身の個性や能力を信頼されていないように感じる傾向があるため、丞のように相手の能力を認めたうえで「少しだけ」境界線を溶かしてくれるような存在は、とても心強い「繋がり」となります。
この記事の冒頭で、「二重性概念は、互いの要素がバランスを取ることで人は健全に生きられる」と書きましたが、この丞のあり方こそ、過剰なエージェンシーを健全な状態に引き戻す、理想的な「緩和」なのです。
誉の輪郭をほんの少し際立たせる東
そんな東もまた、主演の誉を東らしいやり方で支援していきます。
誉は、彼女に言われた「壊れたサイボーグ」という言葉により自分は欠陥品であると解釈をしていましたが、それは果たして本当なのか?と問いかける東。
他者を気遣い関係性を大切にする誉のコミュニオン的なあり方は、素晴らしい美徳であることは東も認めています。しかし、実際に誉はそれが過度になり、自分自身を軽視してしまう…という弊害を生んでいたのも事実です。
そこで東は周囲の人たちに誉を題材にした詩を書いてもらう企画を提案します。どこからこの考えが浮かんだのか!?突拍子もないところがなんとも東らしいです(笑)

(冬組第十二回公演『黄天ノ種火』より)
ここで注目したいのは、東は答えを敢えて教えなかったというところです。
冬組に誉をテーマにした詩を書いてもらい、それを受けたうえで、誉に自分の力で考えてもらう。このプロセスこそが、東が誉に与えたかった機会なのです。
「壊れたサイボーグ!」の言葉を自分の価値そのものであるかのように真に受けてしまった誉にとって、東が「その解釈は間違っていて、こういう意味で言ったんだよ」と答えを提示したところで、またそれを手放しで受け入れてしまっては意味がありません。
なぜなら、自分の価値を他人の言葉で定義しているという構造は何も変わらないから。それでは、誉の健全な自尊心は決して育まれません。
誉の過剰に溶けてしまった境界線を緩和するためには、自分という「個」を自ら認識する必要があったのです。
そして誉は、冬組と監督から詩(?)を詠んでもらうことで、自分が他者にどう認識されているか、どういう価値をもたらしているのかを改めて客観視することとなります。
これまで「自分は欠陥品だ」という主観に囚われていた誉ですが、皆が詠んでくれた詩の内容にはその「欠陥」も含まれていました。
しかし過去の認識と違っていたのは、皆の詩の中ではその「欠陥」も包括した有栖川誉という人間そのものをまるごと承認していたところです!
この新しい発見があったからこそ、誉はかつての恋人が言った「壊れたサイボーグ」という言葉の意味を再解釈することができたのです。
「自分は人の心がわからないから、他者との関係で失敗する」という、誉の心を縛り続けた思い込みが、ここでようやく覆されました。
欠陥があるからといって、他者との「結合」を諦める必要はない。
この気づきが、誉の心を縛っていた思い込みを覆し、共同体の中で受け入れられる、健全な「個」の感覚を、初めて彼に芽生えさせたのです。
つまり、東のアイディアと冬組・監督の協力によって、過剰なコミュニオンを健全な状態に引き戻す「緩和」が成されたというわけですね。
一人では見つけられなかった答え:『黄天ノ種火』における二重性概念
「個」を確立することの危うさを、他者との「繋がり」を支えとして乗り越えた東。一方で「繋がり」に依存する脆さを、「個」を認識することで乗り越えた誉。
二人とも自分とは相反する力に救われ、人間としてもプロの表現者としてもひとつ成長することができたように思います。
そして二重性概念を応用してストーリーを見ていく上で興味深いのは、エージェンシー、コミュニオンがそれぞれ過剰な状態にある人間がバランスを取るために、単に反対の性質を持つ人間が寄り添うだけでは不十分であるということです。
誉の支援をした東も、ただ単にエージェンティックな在り方を教示したわけではありません。
東自身から見た有栖川誉という素晴らしい個性を、誉自身が低く見積もってしまっている現実が見過ごせなかったから、その個性の素晴らしさを自分自身で認識できる機会を与えたという形なのです。
東だけではなく冬組や監督たちすべてが誉の動機の在り方を深く理解しており、受け入れ可能な形で対極の視点を提示できたからこそ、良き支援者となったのかもしれません。
Outro:私が誉を「理解できない」理由
さて、久々にボリューム感のある分析記事を書いてみましたが、いかがでしたでしょうか?
同じ性格タイプの誉のことがわからない!という、筆者の直感から始まったこの探求ですが、まさか記事にするのに約3ヶ月もかかるとは思いませんでした…。
私は当初、『機会仕掛けのクリスマス』も含めストーリーを何度も読んで誉の行動原理について考えてたのですが、「そんな泣いてばかりの女とっとと別れればいいのに…」とか、「私だったら他人が悲しんでいても、別に慰めたり励ましたりはしないな」とか、そんなことばかり思っていたんですよね(笑)
それもそのはず、この記事の分析を通して見えてきた通り、筆者自身、東のようにエージェンシー的な傾向を強く持っているがゆえ、他者との境界線があまり開かれていない。なので、誉の行動が、ただただ不可解に映ったのでしょう。
しかし今回、東という対照的な在り方を通して誉の行動を分析したことで、それはどちらが良い・悪いという話ではなく、単に「動機の方向性」が違うのだと、やっと理解することができました。
同じ16タイプという「道具」を持っていても、その使い道が違えばこれほどまでにキャラクターの印象が変わるというのは、興味深いですよね。
ちなみに、A3!には誉と同じ性格タイプでエージェンシー的な傾向を持つキャラクターも実は登場します。その話は、また別の機会にご紹介できればいいなーと思っています。
この二重性概念は、キャラクターをより深く理解するための有力な概念になりそうですので、これからもこの視点で色々なストーリーを読み解いていくのは面白そうですね。
残念ながら日本語訳された書籍がないのですが、ご興味を持たれた方は英語で検索してみてください。または、大きな大学の図書館でしたら置いていあるところもあると思います。
余談ですが、個人的には冬組メンバー&いづみ、それぞれの詩の内容とか形式がそれぞれ個性出てておもしろいなーと思いました。
詩が上手コンテストではいづみと東が上手!という感じでしたが、詩を書けと言われてトラディッショナルな形式に頼る丞とか、ガイが箇条書きなこととか。謎な選択ではあるけど、でもそれぞれのキャラらしい書き方だよな~という感じで良かったです。
皆さんもよろしければ、再度イベストを読んでみて、お気づきの点があればお聞かせください!
|













コメントを残す